





|
◆広見(ひろみ)
所在:益田市匹見町匹見(ひきみちょうひきみ)
大字匹見の中部南寄り、匹見川支流の広見川(裏匹見峡)沿いにある。
昭和45
|
|||||||||||||||
 写真1 農地跡(以下概ね上流より) |
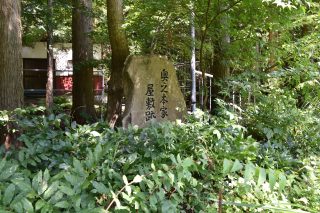 写真2 屋敷跡の碑 |
||||||||||||||
 写真3 屋敷跡。碑が建つ |
 写真4 屋敷跡の碑 |
||||||||||||||
 写真5 屋敷跡の碑 |
 写真6 屋敷跡 |
||||||||||||||
 写真7 開けた平坦地 |
 写真8 校舎 |
||||||||||||||
 写真9 校舎内の一室 |
 写真10 校舎そばの建物 |
||||||||||||||
 写真11 農地跡 |
 写真12 屋敷跡。右に浴槽 |
||||||||||||||
 写真13 水田跡 |
 写真14 川と屋敷跡の石垣 |
||||||||||||||
 写真15 屋敷跡入口 |
 写真16 写真15の屋敷跡 | ||||||||||||||