|
◆護摩堂(ごまどう/ゴマド・ゴマンド)
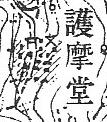
※ この地図は、国土地理院発行の1/50,000地形図「魚津」(昭和37.10)を使用したものである
所在:上市町護摩堂
地形図:越中大浦/魚津
形態:山中に家屋が集まる
標高:約380m
訪問:2011年6月
町の北部、滑川市蓑輪(みのわ)との境にある。集落は大字内の東部。
現在の集落には弘法堂(写真1)や八幡社(写真2)のほか、1軒の宿が営業している。往時の名残として道路脇に蔵が1棟残るほか、廃材が積み上げられた状態の屋敷跡もある(写真4)。弘法堂の脇には「弘法大師の清水」が湧き出ており、訪れる人も多いのか駐車スペースや公衆便所が設けられている。明るくのどかな印象。かつては学校(山加積小学校護摩堂分校、のち冬季分校)があった。
弘法大師にゆかりのある集落で、以下に弘法と集落について町誌や集落内の説明板などから要約したものを記す。
延暦21(802)年、弘法大師(当時29歳)がこの地に巡錫し、しばらく滞在する。その際獣害などに苦しめられていた住民の安寧を願って護摩を焚いたことにより、この地を護摩堂と呼ぶようになる。また現在も湧き出る清水は、水に不便なことを憐れんだ弘法が錫杖で穿ち、湧き出したというもの。
天和2(1682)年、日石寺の僧により大師の霊跡として堂宇が建立され、現在の大師堂のはじまりと伝えている(「(巡錫から)間もなく村人たちによって弘法堂がつくられ…」という記述もある)。弘法の遺書・遺品があったと伝えられているが、数百年前に集落が大火に見舞われ詳細は分からない。
また学校に関する沿革は以下のとおり(案内文ママ)。
| 昭和12 |
公民館兼冬期分校校舎が建てられる |
| 昭和26 |
護摩堂分校発足 |
| 昭和43 |
分校に電話架設 |
| 昭和47 |
分校一時休校 冬期分校とする |
| 昭和48 |
分校休校 |
資料『村の記憶』より、各戸の離村状況は以下のとおり。
| 姓 |
転出時期 |
転出先 |
| 中井 |
明治34 |
町内 |
| 三浦 |
大正10 |
滑川市 |
| 水口 |
大正13 |
東京都 |
| 栗 |
昭和27.3 |
静岡県 |
| 三浦 |
昭和41.6 |
町内 |
| 〃 |
昭和41.12 |
〃 |
| 宝田 |
昭和42.12 |
滑川市 |
| 水口 |
昭和44.4 |
町内 |
| 三浦 |
昭和45.6 |
〃 |
| 〃 |
昭和46.4 |
〃 |
| 〃 |
昭和46.6 |
〃 |
| 中水 |
昭和47.3 |
静岡県 |
| 水口 |
昭和47.8 |
滑川市 |
| 栗 |
昭和47.10 |
上市町 |
| 水口 |
昭和48.4 |
〃 |
| 〃 |
昭和48.10 |
滑川市 |
| 中水 |
昭和48.11 |
町内 |
| 三浦 |
〃 |
滑川市 |
| 宝田 |
昭和49.4 |
町内 |
| 水口 |
昭和49.11 |
滑川市 |
| 〃 |
昭和50.8 |
〃 |
| 山岸 |
平成5.12 |
〃 |
|
|
|
| 三浦 |
― |
(※1) |
|
|
|
| 栗 |
不明 |
高崎(※2) |
| 三浦 |
〃 |
不明 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
| 山岸 |
〃 |
北海道 |
※1 本文には「断」と記載。断絶の意か
※2 群馬県高崎市か
なお大字護摩堂は近世の新川郡加積郷の護摩堂村。明治5年24戸。昭和50年4戸8人。明治22年山加積村(のち上市町)の大字となる(角川)。
|













