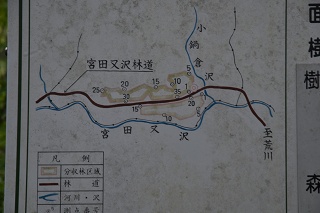|
◆宮田又(みやたまた)鉱山
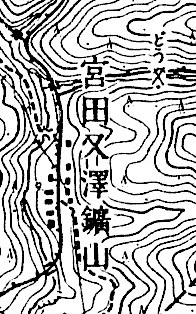
※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「刈和野」(昭和22.1)を使用したものである
所在:大仙市協和荒川(きょうわあらかわ)
地形図:稲沢/刈和野
形態:川沿いに家屋や施設が集まる
標高:約140m
訪問:2018年5月
大字荒川の中部、宮田又沢川(雄物(おもの)川四次支流)沿いにある。銅を産出した宮田又鉱山に伴う鉱山集落。
町史や資料『宮田又鉱山誌』より、主な変遷は以下のとおり。
| 享保7(1722) |
下荒川村の多治兵衛が発見したといわれる |
| 元文2(1737) |
「宮田銅山」として採掘開始。湯埜沢・大鍋倉・足倉山・成土石・安藤滝の5山 |
| 享和年間(1801-04) |
鍋倉鉱山と改称し秋田藩が試掘したが、間もなく放棄 |
| 明治4 |
境(さかい)(※1)の宮司物部氏および会津藩士の野出氏により再興。数年後休山 |
| |
(この間、数度の経営者の変遷を経る) |
| 明治40 |
金沢市の横山工業部の経営となる。大正初期に放棄 |
| 昭和8秋 |
横手市の鉱山師熊谷富治により探鉱が行われ、大鍋倉沢に大鉱脈を発見。宮田又鉱山株式会社を設立し、翌年鉱業権を取得 |
| 昭和14 |
この年発見された鉱脈(眠牛鉱)の開発計画を巡り、熊谷氏ら促進派と現状維持派が対立。促進派が敗れ、熊谷氏が退任したことにより会社は経営危機に陥る |
| 昭和15.3 |
帝国鉱業開発株式会社が買収 |
| 昭和17秋 |
大規模な鉱床(裸馬ひ)(※2)を発見(閉山までの主要な鉱床となる)。 |
| 昭和18 |
「宮田又鉱業所」を「荒川鉱業所」と改称 |
|
昭和25 |
帝国鉱業開発が解散し、新鉱業開発株式会社が継承 |
| 昭和40.9.13 |
閉山 |
※1 後の協和町境
※2 「ひ」は鉱山用語で鉱脈を指す。「金へんに通」。また「裸馬(らば)」は、社長菅氏の俳号
また就労者数の推移は以下のとおり(昭和25年以降は9月期〔4月〜9月〕)。
| |
昭和15 |
昭和17 |
昭和18 |
昭和19 |
昭和20 |
昭和21 |
昭和25 |
昭和26 |
昭和27 |
昭和28 |
昭和29 |
昭和30 |
昭和31 |
昭和32 |
昭和33 |
昭和34 |
昭和35 |
昭和36 |
昭和37 |
昭和38 |
昭和39 |
| 職員 |
14 |
16 |
|
|
|
|
12 |
15 |
17 |
20 |
18 |
19 |
21 |
20 |
20 |
20 |
23 |
23 |
20 |
22 |
20 |
| 鉱員 |
35 |
120 |
|
|
|
|
113 |
150 |
191 |
201 |
198 |
196 |
225 |
220 |
199 |
190 |
188 |
181 |
175 |
151 |
129 |
| 計 |
49 |
136 |
93 |
109 |
101 |
71 |
125 |
165 |
208 |
221 |
216 |
215 |
246 |
240 |
219 |
210 |
211 |
204 |
195 |
173 |
149 |
※3 昭和18年から同20年にかけて朝鮮人労働者も従事していたが、この表には含まれていない。第一次徴用の昭和18年には40名、第二次の昭和19年には45名が徴用された
主な施設として、街区に共同浴場・保育所・診療所・理髪所・消防用詰所・組合事務所・供給所・鉱員社宅・合宿所・小学校・山神社・製材所、大鍋倉沢沿いに採鉱事務所・選鉱場・ズリ捨て場などがあった(昭和38年。概ね入口に近いものより)。以下特記。
(診療所)
昭和20年5月より、船医であった金子氏が「衛生管理人」という肩書で診療を開始。市街地の医師の指示を受けながらの従事であった。昭和28年より加我氏が赴任。翌年金子氏が帰郷し、閉山まで加我氏が「衛生管理人」を務めた。昭和31年頃には、協和診療所より歯科医師が出張診療を行っていた。
(供給所)
食料品・日用雑貨の商店。
(社宅)
職員社宅8棟15戸、鉱員社宅二戸長屋13棟26戸、同四戸長屋18棟72戸。ほか境駅前にも2棟4戸があった。
(合宿所)
職員合宿1棟、鉱員合宿1戸。ほか境駅前に「境寮」があり、来客の接待や従業員とその家族の旅行の際の一時的な宿泊所、子弟の高校通学のための寄宿舎に利用していた。
(小学校)
宮田又小学校。主な沿革は以下のとおり。
| 昭和18.2 |
大盛(たいせい)尋常高等小学校宮田又冬季分教場として開設(※3)。飯場の一部を間借り |
| 昭和18.4 |
閉鎖。児童は徳瀬分教場に通学 |
| 昭和19.1.6 |
冬季分教場再び開設 |
| 昭和19.12.28 |
新校舎に移転 |
| 昭和31.4.11 |
独立。宮田又小学校となる |
| 昭和40.12.31 |
閉校 |
※3 町史では冬季分教室とある。また日付は26日とある
また児童数の推移は以下のとおり(赤字は最多。昭和18年〜20年4月および同21年9月〜22年までは、1年生から4年生までの在籍)。
| 昭和18 |
昭和19 |
昭和20.4 |
昭和20.7 |
昭和20.11 |
昭和21.4 |
昭和21.9 |
昭和21.12 |
昭和22 |
昭和24.1 |
昭和24 |
昭和25 |
昭和26 |
昭和27 |
昭和28 |
昭和29 |
昭和30 |
昭和31 |
昭和32 |
昭和33 |
昭和34 |
昭和35 |
昭和36 |
昭和37 |
昭和38 |
昭和39 |
昭和40 |
昭和40.12 |
| 24 |
41 |
43 |
70 |
50 |
54 |
29 |
23 |
25 |
53 |
60 |
64 |
74 |
73 |
79 |
78 |
不詳 |
92 |
84 |
116 |
103 |
107 |
111 |
102 |
85 |
87 |
71 |
4 |
なお中学生は荒川鉱山の朝日中学校大盛分校に通学していた。
現在は植林地の中で僅かに遺構が散見されるのみ。現地の手前、徳瀬集落の三叉路には案内と解説の看板が立てられている(写真1)。
|