|
◆追切(おいきり)
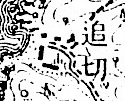
※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「〓【魚へんに毛】崎」(昭和28.1)を使用したものである
所在:宮古市重茂(おもえ)
地形図:閉伊崎/〓【魚へんに毛】ヶ崎
形態:河口に家屋が集まる
離村の背景:災害
標高:数m
訪問:2019年11月
重茂北地区(大字重茂のうち、重茂半島の部分)の北西部、宮古湾に面した入り江にある。
平成23(2011)年3月の東日本大震災により被災。全域が浸水し、すべての建物が流失もしくは全壊(※)。集落の入口には、津波の到達地点を示した石碑が建てられている(平成26年3月11日、北地区民による設置)(写真1)。
資料『東日本大震災宮古市の記録』では、平成28年度の高台移転の予定戸数を追切・浦ノ沢2戸としている。
市史によると、当時(平成6年刊行)で4戸。うち3戸は木村家で、1戸は山林所有者の家(岩泉からの来住者で、当時2代目)。木村家3戸の屋号は、「カサノイエ/ウエ」「ナカノイエ」「シタ」で、「ナカノイエ」は木村家の本家。
また「カサノイエ」では水神様、「ナカノイエ」では八幡様、「シタ」ではテンノウサマ(八坂神社)を祀っていた(重茂北区では各集落の氏神はなく、各家で屋敷内あるいは屋敷近くに「氏神」を祀るという形態になっている)。水神様はもと家の横の柿の木の隣にあったが、のち浜近くへ移した。また八幡様は浜の向かいの山の上にお宮を作った(明治末期か大正初期)。またテンノウサマ(八坂神社)は家の近くの小山の途中にある。昔家の人が旅に出て、八坂神社で授かったお札を祀っている。
なお「追切」という呼称は仲組地区よりも北(大程・追切・笹沢・浦ノ沢)の広域地名としても用いられるとのこと。
以下は参考までに、重茂北区の稼業の概況から当地にも該当すると思われる記述を抜き書きしたもの。
以前は半農半漁であったが、現在農業は自給用の生産のみ。米はほぼ皆無。
漁協には全戸が加入し、人々は天然または養殖のワカメ・昆布やウニ、アワビなどの磯漁、サケの定置網漁で収入を得ている。ほとんどの家は小型の船で磯漁に従事するか、定置網漁の乗組員として漁協に雇用される形で漁業に携わっている。
大半の人が副業を持っており、漁業関係の仕事が少ない時期には宮古などへ水産加工業、出稼ぎに行くなどしている。
※ 復興関連の資料「第2回地区復興まちづくりの会 重茂北地区(追切、浦の沢、鵜磯、荒巻)、音部地区、重茂里地区、重茂南地区(千鶏、石浜、川代)」の「被害の状況」より
| 
















