|
◆金浦(かなうら)
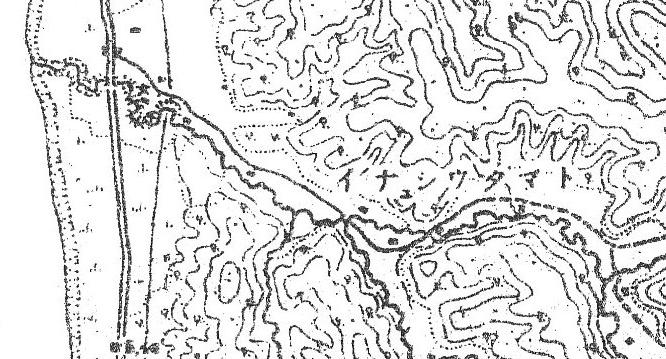
※ この地図は、内務省地理調査所発行の1/50,000地形図「遠別」(昭和22.2)を使用したものである
所在:遠別町金浦
地形図:遠別/遠別
異表記:トマタウシュナイ(旧称)・苫年内(とまとしない)(旧称)
形態:河口から川沿いにかけて家屋が散在する
離村の背景:(1世帯現住)
標高:数m〜20m弱
訪問:2012年6月
町の西部、トマタウシュナイ川沿いにある。
以下は町史の記述。
もと御料地であったものが明治34年解除され、明治35年より開墾が始まる。開墾の草分けは栗崎氏。明治時代12戸、大正時代9戸が入植した
漁業では、明治38年ニシン漁開始。同40年には海難でこの地に居住した3名も加わる。大正期には4戸が加わり、秋田県人が多数を占めていたため一時期は「秋田漁場」と呼ばれたこともあった。昭和29年からの不漁により、漁家は減少
昭和14年、字名改正で「苫年内」から「金浦」となる。由来は「農又ハ一部海浜部落なる故魚ノトレル浜ノ意ヲ含メ名付ケル」。大正7年「北華(ほっか)」と称したこともあったが、これはすぐに消滅
現在は他集落からの通いで、荒廃しかけた耕地を再興。豆類・甜菜・ジャガイモなどを栽培
(小学校沿革)
| 明治40.4.15 |
トマタウシュナイ特別教授簡易場設置 |
| 大正6.9 |
トマタウシュナイ特別教授場と改称 |
| 昭和2.4.1 |
苫年内尋常小学校と改称 |
| 昭和16.4.1 |
金浦国民学校と改称 |
| 昭和22.4.1 |
金浦小学校と改称 |
| 昭和37.11 |
校地移転 |
|
昭和53.3.31 |
廃校 |
(児童数の推移。抜萃)
| 昭和30 |
昭和35 |
昭和40 |
昭和41 |
昭和42 |
昭和43 |
昭和44 |
昭和45 |
昭和46 |
昭和47 |
昭和48 |
昭和49 |
昭和50 |
昭和51 |
昭和52 |
| 51 |
63 |
38 |
29 |
20 |
15 |
16 |
14 |
17 |
15 |
11 |
9 |
7 |
6 |
3 |
「角川」によると、昭和26年54戸373人、昭和61年10戸20人。神社は金浦神社。
現在も川沿いの農地では通い耕作が行われており、訪問時も農作業をする方々を多く見かけた。国道沿いには広く牧草地が広がるほか、畑や「金浦原生花園」(写真5)がある。原生花園では時期に応じ、エゾカンゾウ・イソツツジ・ヒオウギアヤメといった花々の群生を楽しめる。かつては集落に天塩金浦駅があったが、位置は未確認。学校跡は金浦バス停付近にあり、現在も門柱がその名残を見せる(写真8)。
集落で会った方の話によると、古くからの家が1軒現住のほか、5組が通い耕作で訪れているという(うち元々の住民は3組)。かつての農産物はほとんどが米(小作農)であったが、現在は小麦・ビート・ジャガイモ・ソバ・豆類などの畑作物。教員住宅は集会所として転用された(現在はない)。
|













